
私が料理の道に進もうと思ったのは、学生時代のアルバイトがきっかけでした。私の家系はみんな飲食業に携わっており、そのつてでホテルの中のレストランでアルバイトをしたのです。そこで最初に食べた料理が山形牛のしゃぶしゃぶだった!!
食べ盛りの学生にとってこんなに嬉しいことはありません。「ここで働けば、これを毎日食べられるのかな…」と単純に期待しましたよ(笑)。今にしてみれば、私を飲食の世界にいざなうための親たちの策略だったのかもしれませんが…(笑)。
小さな頃から何かを作ることがとても好きだったので、バイト先で覚えた料理は家でも作ってみました。両親は満面の笑みで喜んでくれ、子供ながらにそれが嬉しかったのかもしれません。こうして私の料理人人生の最初のお客様は両親となりました。
その後、日本料理店に勤め、約10年間の修行時代を送りました。その間、辛いこともたくさんありましたが、それでも辞めなかったのははやり料理を作ることが好きだったからだと思います。
日本料理はとても基本に忠実な料理です。例えば、春になれば筍を使い、夏はハモ、冬は鍋料理…。これらを毎年繰り返す。日本料理の伝統とも言える礎の部分を理解すればするほど、そのすばらしさに感心しましたが、一方で「これで本当に自分の料理と言えるのだろうか」と、疑問も感じていました。
シンプルなのはいいのだけれど、何かが足りないような…。食べ終えた時に何を食べたのかわからないほど印象が薄い時だってある―こんなふうに自分の料理に行きづまりを感じていた27歳の時、たまたま舞い込んできたのがフランス行きの話でした。
それはフランス・パリのオペラ座近くにある日本料理店「伊勢」で働かないかという話でした。何でも、世界的に有名なデザイナーたちが接待などに利用する話題の店なのだとか。「料理人として、新しい扉を開けられるかもしれない」と期待し、渡仏を決断しました。
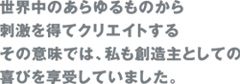
案の定、フランスの豊穣な地が私に大きな収穫をもたらしてくれました。海外では日本料理店というだけで、ある種のブランド力が存在しました。お客様は“ジャパニーズ・レストラン”に大いに期待して来店される。だからちゃんとしたものを提供しなくてはいけない。大げさかもしれませんが、日本の食文化を背負った伝道師になったような気分で働いていました。だから「里芋の煮っころがし」のような定番の家庭料理も手を抜かずにきちんと調理しました。それは心地よいプレッシャーでした。
お客様はパリコレで活躍するデザイナーなど、世界中の一流を知り尽くしたお客様ばかり。一度の接待費用が何十億円ということもありました。つまり価格が青天井の世界なのです。当然、料理人の腕も一流を求められます。精神的にも肉体的にも追い詰められることもあり、寝る間も惜しんで料理のことを考えました。休日も三ツ星レストランや中華街などに積極的に出かけて情報を収集し、感性を研ぎ澄ましました。
私が季節ごとに料理の表現を追及するのと同じように、デザイナーであるお客様もまた、春夏秋冬のコレクションなどを通して、四季折々の美を追求していました。彼らの世界観にある洋服や靴のイメージと、私の料理の色づかいや食材のバランスなどクロスさせながら楽しんでくれました。世界中のあらゆるものから刺激を得てクリエイトするという意味では、私もお客様も同じクリエーターであり、創造主としての喜びを享受していました。
農業国であるフランスの食材にも存分に触れることができました。フランスでは、うに、かき、ムール貝などの貝類の味が濃厚なのです。それらを使った調理法に料理人魂が揺さぶられましたね。でも、かつおぶしと乾燥わかめだけは日本の素材にこだわり、いつも築地から送ってもらっていました。
本場のワイン文化にも触れることができ、現在のパートナー・丸山宏人氏(オザミワールド 社長)と出会ったのもこの時でした。ワインを楽しめる日本料理店「銀座大野」がフォアグラなどを使ったりしているのも、この頃の経験が生かされているからなのです。
このようにして、フランスでの5年間は、一流デザイナーたちの感性にも大いに影響を受け、表現者としても成長することができました。その間、自分に言い聞かせていたことは、「易きに流されるな」という言葉。一度あまさが身についてしまうと、帰国した時に日本で勝負ができなくなってしまうという危機感を持ちながら働きました。そういう姿勢が、もしかしたら今回のミシュランでの星獲得につながったのかもしれませんね。



